お客様の見本の幕やご希望を基に、当店で校正したものを事前確認して頂いての製作になりますので、仕上がり前にイメージが掴んでいただけます。
| 白地に黒のイメージ | 色地に白抜きのイメージ |
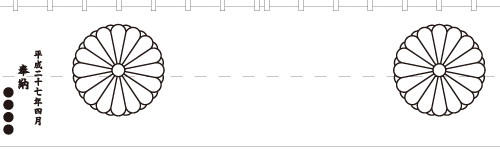 |
 |
以下のリンクボタンから簡単入力で見積もり依頼していただけます。
当店の神社幕・寺院幕の特徴
諸説ありますが、一説には起源が平安時代とも云われる伝統手染「引き染め」で染めていますので、裏側までしっかりと染料が浸透しており、色に深みがあります。当店では、型をデジタルデータで管理しており、追加で幕が必要になった場合などは、前回のデータを利用して専用のマシン(カッティングプロッター)で製版しますので、紋や文字などの再現性が非常に高くリピート時もご安心頂けます。染料は、綿などの天然繊維の染色に使用される染料の中で最も堅牢度が高い反応性染料を使用しております。神社仏閣系統の幕は一般の幕と比較にならないほど大きなサイズのものがありますので、二幅を繋ぎ合わせたり、大きなものに小さなパーツを取り付けたりなどの高い縫製技術が必要とされますが、当店では長年縫製も自社製造で対応してきましたので、ご安心してご注文ください。
おおまかな作業工程
製版
データ作成で作ったアウトラインデータを元にプロッターで型紙をカットし、型枠に貼ります。

型糊置き
製版工程で完成した型を利用して防染糊を置きます。糊が置かれた部分が、最終的に白で染め上がります。

調色
お預かりしている見本を参考にして粉末染料の配合をし、染料(液体)を作ります。一度作った染液は調整が出来ませんので、予想と違った色になった場合は最初からやり直しとなるので、かなりの時間をかけます。過去に作成したカラーサンプルが調色のための財産と言っても過言ではありません。


染色(引き染め)
刷毛を利用し生地に染料を引きます。時間をかけすぎるとムラになるので手早くきれいにリズミカルに引いていきます。染物屋らしいダイナミックな工程で、見応えがあると思います。

水元・色止め
染色後、生地全体に溶剤を、刷毛を使用して塗ります。所定の時間放置し、化学反応で染まり、その後不純物や余剰染料を除去するために水元工程にて洗います。

縫製
仕上がり寸法になるように裁断し、生地端を縫い、チチを取り付けて仕上げアイロンをかけて完成です。

見積もりの流れ
下記事項をお問い合わせフォームよりご連絡いただけますと、スムーズなご対応が可能です。
-
- 寸法:高さ×横幅
- 紋:家紋の種類を記入ください。家紋名が分からない場合や家紋帳等に載っていない場合は現在の家紋の画像を当店メールアドレスに送信ください。
- 紋数:幕に入れる予定の紋の数
- 文字数:年号、寄進者、奉納等の文字の総数
- 色:紫地に白抜き、白地に黒文字など詳細にお伝えください。
- 仕立て仕様(任意):幕上にあるチチと呼ばれる幕紐(ロープ)を通すための輪の配置、数等の仕立て仕様に特にご指定がない場合は、当店の定番仕様での見積となります。
- 付属品の有無
- 揚巻房:必要な場合は具体的にお伝えください。色、寸法等 色のみの指定の場合は寸法に関しては幕寸法に適した当社既定の寸法のものをご用意します。
- 幕紐:必要がある場合は具体的にお知らせください。例)白と紫、白と黒と青の3色など
- 生地のご希望:綿、化繊などをお知らせください。綿の場合60ブロード、天竺、化繊はポリエステル縮緬となります。
| 生地の種類/特徴 | メリット | デメリット |
| 綿:60ブロード | 綿生地の中では、やや光沢があり高級感がある薄手の生地で、幕によく使用されています。 | 価格が天竺と比べてやや高め。生地巾の上限が約110㎝なので、高さが110㎝以上の幕ですと縫い合わせになります。 |
| 綿:天竺 | 生地巾が60ブロードよりも広いものがあります。高さが120㎝以内の幕ならば一枚もの(縫い合わせなし)で製作可能です。 | 光沢がないので、60ブロードと比較すると高級感がなく感じます。 |
当店調べ